第3条 再生資材の利用
再生骨材等は、工事現場から40kmの範囲内に再資源化施設があり、かつ、再生資材のストックが確認された場合、下記の要件に従い、建設工事において可能な限り使用しなければならない。また、設計図書においても再生資材の使用を明示しなければならない。なお、再生資材のストック量は、建設副産物管理システムを利用し確認する事が可能である。また、各工事間において再生資材使用量の調整が必要な場合、建設副産物対策連絡協議会の各ブロック会議において調整しなければならない。
1.基礎材、裏込材等の利用
基礎材、裏込材等の用途に利用できる再生資材は、所定の品質基準を必要としない無規格品(最大粒径40mm、80mm)とする。なお、安定計算を必要とする重要構造物の基礎材等には、無規格品は使用しないこととする。
再生資材は新材に比べ若干品質は落ちるが、安価であり、品質基準を必要としない「基礎材、裏込材等」には積極的に使用しなければならない。無規格品のストックがない場合は、規格品の再生資材と新材を比較し、経済的な資材を採用する。
なお、基礎材、裏込材等に使用する再生資材は、アスファルト塊混入率等特に定めない。
2.下層路盤材、歩道路盤材の利用
下層路盤材及び歩道路盤材としての用途に利用できる再生資材は、再資源化施設から搬入され、かつ、下記の品質基準を満足するものとする。なお、上層路盤材には、所定の品質基準を満足する再生資材が流通していないことから、当面使用しないこととする。
1)品質基準
a:すり減り減量
下層路盤材、歩道路盤材等に用いる再生骨材は、すり減り減量が50%以下でなければならない。なお、試験方法は、「ロサンゼルス試験機による粗骨材のすり減り試験方法(JIS A 1121準拠)」によるものとし、粒度は道路用砕石S-13(13〜5mm)とする。
b:粒度範囲
再生骨材の望ましい粒度範囲は、下表のとおりとする。なお、試験方法は、骨材のふるい分け試験方法(JIS A 1102準拠)によるものとする。
再生骨材の望ましい粒度範囲
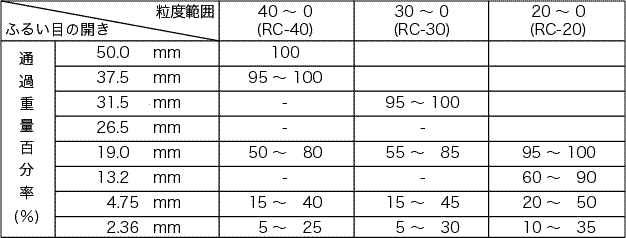
(注)再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。
c:修正CBR
下層路盤材、歩道路盤材等に用いる再生骨材は、修正CBRが下表の数値以上でなければならない。なお、試験方法は、修正CBR試験方法(JIS A 1211に準拠したKODAN A 1211)によるものとする。
工種別毎の修正CBR値
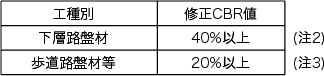
〔注1〕「歩道路盤材等」には、簡易舗装に用いる路盤工等を含む。
〔注2〕アスファルト再生骨材を含む下層路盤材料でも等値換算係数が新材と変わらない修正CBR 値を採用している。なお、コンクリート再生骨材は、調査の結果、すべて修正CBR値40%以上を満足している。
〔注3〕簡易舗装の場合、上層路盤工及び基層・表層の合計厚で30cmを境に目標とする修正CBR値が異なってくるが、本県の場合ほとんどが30cm以下のため、合計厚によらない修正CBR値を採用している。
d:アスファルト塊混入率
再生骨材に配合できるアスファルト塊は、70%(*)を上限とする。ただし、再生骨材にセメントや石灰による安定処理などを施した場合はこの限りではない。なお、アスファルト塊混入率は、下式による。
| As | X 100(%) | As:アスファルト塊 Co:コンクリート塊 |
|
| Co+As |
(*):「プラント再生舗装技術指針」及び県独自調査結果による
aからdに記載のないものについては、「プラント再生舗装技術指針((社)日本道路協会)」を参照すること。